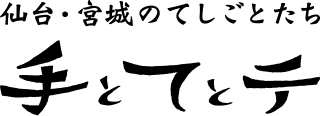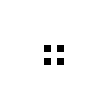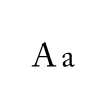10畳ほどの小さな作業場。
そこで松川だるまが生まれます。
仙台の中心部ほど近く。オフィスビルが多く立ち並ぶ、大通りのすぐ脇の路地に「本郷だるま屋」はあります。
自宅に併設する作業場。その中でせっせと筆や刷毛を動かし続ける職人の手によって松川だるまや張子玩具が生まれます。
仙台張子の代表格である松川だるまの大きさは3寸(約9cm)から3尺(約91cm)。
年間5000~6000体制作され、小さいものも合わせるとそれ以上になることも。
本来は信仰品としてお正月時期に買い求められていたため、だるまは冬場に限定して作られていました。
しかし最近の民芸品としての人気の高まりからか、季節を問わず購入する人も増えたため、
現在では一年を通してだるまが作られています。

正月を控える11月から12月がだるま作りの最盛期。分業しながら丁寧に作られただるまが部屋いっぱいに並びます

通学路になっている通りに面しているため、往来する人が作業をのぞいたり、声をかけてくることも

絵付けに使う顔料。胴体脇の梅やお腹の彩色で使われる明るい黄緑色は本郷家のだるまの特徴のひとつ
時代の流れとともに。
だるまさんの今昔物語。

本郷家初代が松川だるまの創始から受け継いだ、歴史ある木型。現在でも大切に使われています
黒光りを放ち、どっしりとした威厳ただようだるまは、
なんと江戸時代から使われている松川だるまの木型。
昔ながらの松川だるまはこの型に食用油を塗り、
角又(つのまた)という海草を煮詰めたものを糊にし、
仙台で作られている柳生(やなぎう)和紙を一枚一枚手ばりして、体(生地)を作ります。
天日干しをして乾燥させたら型から小刀で切り出してはずし、
切り口を同じく和紙で貼り付け、底に起き上がりのもとになる粘土を接着。
お腹に宝船や恵比寿などの“置物”を据えて、ようやく生地が完成します。
ここまでの作業だけでも途方もない時間と労力を要していました。
昔はどこの地方のだるまも和紙を手ばりしてだるまを作っていましたが、
今はあらかじめ成形した生地を使うだるまが主流になっています。
その理由は手漉き和紙を作る工房が少なくなったことなどによる、
原材料の高騰化や生産効率を上げるためなどさまざま。
創始者の名前を冠した松川だるまの名とその流れを大切にしながらも、
時代とともにだるま作りは少しずつ変化しています。

柳生和紙のだるま紙を手ばりした、昔ながらの材料、工程で作られた貴重なだるま生地

型に粘土をつめて天日干しした、底につける起き上がり。コロンと倒しても起きるのは粘土のおかげ
白から赤へ。
下地作りはお天気との戦い。
ベースとなる生地ができたら移るのが「胡粉(ごふん)塗り」の工程。
胡粉とは貝殻を乾燥させて砕いた粉末をニカワで溶いた塗料で、
メイクでいうところの、ファンデーションを塗る前の化粧下地のようなもの。
胡粉を塗ることによって強度が増し、彩色がより際立つだるまになります。
一つ一つ刷毛でしっかりと胡粉を塗った生地は、店の前にしつらえた棚に並べて天日干しに。
3時間ほど干したあとは顔以外の全体を赤一色にする「赤塗り」。
赤く染まっただるまは再び店先に並べて乾燥させます。
つるんと赤く照り輝く後ろ姿はまるで、露店で売られているりんご飴のよう。
天日干しをするこの二つの作業は天気や気温に左右されてしまう、まさに日和見の工程。
職人さんは天気予報とにらめっこしながら、だるま作りの予定をたてているのです。

店先でゆっくりと天日干しに。気温や天候で発色の仕上がりも変わってきてしまうそう。

一つひとつ、とろみのある胡粉をムラなく刷毛で塗り重ねていく「胡粉塗り」

胡粉のおしろいをつけただるまに赤い衣をまとわせる「赤塗り」もすべて手作業
縁起をかつぐ。
きらびやかな装飾で福を授けます。
「赤塗り」が終わったらだるま作りもいよいよ大詰め。
顔に肌色を塗ったら、眉や髭、口などを描き、「絵付け」の作業に入ります。
群青色で顔の周りをぐるりと縁取ったら、そこへ伊達の武将が好んだ金粉をハラリ。
さらにその上には職人さん達が“ぽてぽて”と呼ぶ、海老熨斗(のし)を表した水色の玉模様をちょんちょんと。
胴体脇には“寿”の字を書きくずした梅の木に花がほころびます。
迷いもなく筆を走らせて彩られただるまは、まさに縁起のいい物づくし。
艶やかな毛の眉と浮き上がりの船が豪華な「宝船」、恵比寿さんや大黒さんの置物が鎮座する「玉入り」、
シンプルな彩色の「並」の3種類は装飾がそれぞれ異なります。どの松川だるまを選ぶかは、各家庭のお好みで。

歌舞伎役者のような目の周りのオレンジの彩色は“すっこみ”と呼ばれ、表情に深みを与えます

松川だるまにかかせない群青色を顔の前面いっぱいに。赤から青にスタイルチェンジです

細かな彩色や装飾がほどこされただるまが次の作業を今か今かと待ち構えています
肝心要の目入れ。
仕上げは男の人の役割です。
松川だるまと他の地方のだるまの大きな違いは青い姿と黒々とした瞳があらかじめ描かれていること。
目は空白で、願かけしながら片目を入れ、その願いが叶ったらもう片方の目を描き入れるという、
「開眼」を行うだるまが数多くありますが、松川だるまにはその概念は伝わっていません。
四方を広く見据える大きな黒い目がしっかりと輝いています。
本郷家ではひげと口、目入れは昔から男性の仕事なのだそう。
慣れた手つきで、でも一筆ひと筆丁寧に。
最後に目を描き入れることで“芯”がこめられ、ようやく松川だるまが完成します。

黒々とした瞳が男の人の手によって描かれ、青いだるまさんが完成

たくさんの手をかけて生まれた松川だるま。子どもの健やかな成長、家内安全を願って。
※写真は平成26年、青葉区柏木の工房。現在は仙台市青葉区川平4-32-12に移転しています。