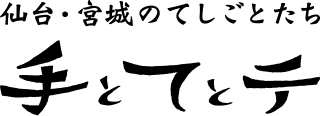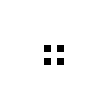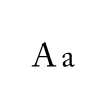仙台御筆の伝統を今に伝える、ただ一人の筆師。
300人の足軽が居住したことにその名が由来するという三百人町(仙台市若林区)。仙台藩が足軽たちの内職として推奨したことから、この地で筆づくりの伝統が受け継がれてきました。「大友毛筆店」の大友博興(ひろおき)さんは、現在も変わらず三百人町で筆をつくり続けています。
大友さんの家は代々足軽の家系で、初代が明治8(1875)年に「大友毛筆店」を創業。大友さんは、4代目にあたります。3代目のお父さんの代には野球チームをつくるほどたくさんの職人を抱えていた時期もあったと言いますが、大友さんがまだ中学生の時に3代目が他界。 大友さんは先代のもとで働いていた筆師に学び、高校に入った頃から筆づくりをはじめたそうです。10年ほど前までは職人と2人で働き、数年前まで近所で筆をつくっていた方が他にもいましたが、今では大友さんが仙台でただ一人の筆師となりました。
各工程が分業化されている他の産地とは異なり、一人の職人が一貫した手仕事でつくりあげる仙台御筆。数段階の長さの毛を、独自の配合で組み合わせていきますが、「本当にちょっとしたこと(毛の配合)で書き味がガラッと変わる」のだそう。大友さんは指の腹に穂首を当てただけで、どの長さの毛がどれだけ足りないのかを判断し、調子をとっていきます。
「上手に筆がつくれる、というだけではだめなんです」と話す大友さん。書家が求める筆をつくれないと、筆師の仕事は務まらないと言います。「10年やっても一人前になれるか、なれないか」という厳しい道で50数年の経験を積み上げ、著名書家の注文にも数多く応えてきました。「そうした周りの人に恵まれて、今があると思っています」。伝統を守り抜く筆師の言葉は、とても謙虚で穏やかでした。

指の腹で穂首の状態を確かめる大友博興(ひろおき)さん。大友さんの筆は、「西川玉林堂」と「おかや」(ともに若林区荒町)で取り扱っている。
<1>「大友毛筆店」に残る、昭和初期の馬毛の御筆。軸には象牙や紫檀(したん)、銀糸が使われている。<2>職人たちで野球チームをつくっていた昭和10年前後の写真。<3>職人の弟子入りに関する書状も数多く残されている。
仙台ならではの一貫した手仕事による筆づくり
-


1. 毛筆の“羊毛”とは中国・山岳地帯のヤギの毛。原毛の長さや質をみて、穂首のどこに使うかを見極める。煮沸、灰で毛もみの後、クシで綿毛を除く。
-


2. 毛先のない切れ毛など不要な毛を取り除く作業が繰り返し行われる。ハンサシという道具で巧みに悪毛を引っかけ、すばやく的確に引き抜く。
-


3. 毛先を揃えて根元を切った数段階の長さの毛を、濡らして組み合わせる。ハンサシを使って何度も薄く広げては折り返し、毛を練りまぜていく。
-


4. 筆づくりに欠かすことのできないクシ。作業をとおして幾度となくクシを入れるので、金属製でも「5年ほどですり減って使えなくなってしまう」そう。
-


5. 指の上で穂先を回転させて状態を確かめながら、毛の量やバランスを整えていき、ツボという筒状の道具に通して太さを揃える。これで芯が完成。
-


6. 乾燥させた芯に上質の上毛(うわげ)を巻きつけて乾かす。麻糸の一方を口にくわえて根元にかけ、焼きごてをあてたら、すばやくきつくしばる。
-


7. 軸を回転させながら、クリハという細い小刀で穂首をはめる部分を削って調整する。あっという間の早技で、穂首がぴたりとはまっていく。
-


8. 最後に水で溶いたフノリをつけて仕上げる。「毛の一本一本にフノリを充分に含ませる」ため、たっぷりのフノリに穂首をしっかりと浸す。
-


9. 糸の一方をくわえて穂首に巻きつけ、筆を回しながら余分なフノリを取る。滑りが良い絹糸で、「2割りくらい残すように絞る」そう。乾かして完成。