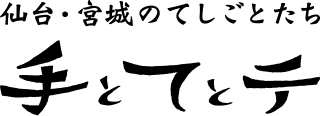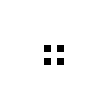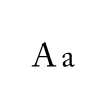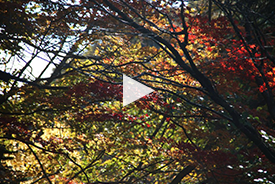「土があって、形があって、
釉薬があって、窯があって、
使ってくださる方がいて、作る側の人がいて、
総合して堤焼です」
4代・針生乾馬さんを中心に、
長男の久馬さん、次男の和馬さんをはじめとする
ご家族みなさんが力を合わせて働く堤焼乾馬窯。
その歴史や堤焼のこれからについて
お話をうかがいました。

堤焼の土は「ふしぎな土」
堤焼のはじまりは、元禄年間(1688〜1703年)に江戸の陶工・上村万右衛門が仙台に招かれて来て、堤焼のもとになる「杉山焼」が作られるようになった頃とされています。堤焼乾馬窯の4代・乾馬さんによると、昔、杉山という山が現在の台原(だいのはら/仙台市青葉区)のあたりにあって、「そこから採った土で作ったのが杉山焼だった」のだそう。
「ただ資料によると1601年頃から仙台城がつくられ、その後城下町ができ、そこで必要な日用雑器を作るために、杉山の土を使って堤町に住んでいた下級武士たちを中心に堤焼のもとができる、とあります。そうすると焼き物づくりは、上村万右衛門が来るちょっと前からすでに始まっていたと考えられます」と話すのは、乾馬さんのご長男・久馬さん。「万右衛門のより良い技術指導によって形に江戸風のものが取り入れられ、堤焼の“基礎が固まった”と考えられる」そうです。
現在でも堤焼の土は、「台原にあった警察学校の跡地から掘ったものを使っている(久馬)」といいます。「宮城県警の方々に『粘土が出たら掘らせて下さい』とお願いしていたのですが、警察学校が移転するときに連絡をもらい、私らが生きてるうちは間に合うくらい大量の土を、更地になった警察学校跡から許可をいただき運びました」と乾馬さん。
その時採掘に立ち会った久馬さんは、現場で土質の良さを目の当たりにしました。「台原には良い粘土層があるとよく言われていたんですが、実際に掘ってみたら、本当に出てくる土、出てくる土、全くよけいなものが混ざっていない、きれいな粘土なんです。隣接する堤町に焼き物の町ができるわけだと、あれを見て思いましたね」。
昭和初期、水甕(みずがめ)などの大物が、民藝の父・柳宗悦から高い評価を受けた堤焼。“強くて粗い”などと表現されることの多い堤焼の土ですが、乾馬さんは、「土がはじめから大物に向いていた、ということではありません」ときっぱり。ただ「大きな物を焼くだけの火力にもつ、高温に耐える土」なのだそう。土の特性だけではなく、それを最大限に活かしていく職人の修錬の積み重ねがあってこそ、堤焼の大物が生み出されたのだといいます。
「研究者の方がきて堤焼の土を調べたときには、『訳の分からないふしぎな土だ』と言っていました(笑)」と久馬さん。「高温には耐えるし、その一方で、粗い土だとろくろが引きづらいものなのですが、そういうこともなくちゃんと形づくることもできる。両方を合わせ持った土なんですね(久馬)」。
乾馬窯は、日本に唯一現存する『乾山秘書』を受け継いでいることでも知られています。「初代乾馬の師匠の三浦乾也(6代・乾山)が受け継いだのが尾形乾山(※)の秘伝書です。現在の堤焼は絵付けはしないので、釉薬だったり、形だったり、または精神的な部分だったり、そういったものを受け継いでいます。『乾山秘書』をみると、土作りなんかは、今でもほんとに書いてあるとおりにやってるんだなって思います(久馬)」。
釉薬には地元で採れる早坂岩・赤岩などを昔から用いていますが、仙台市内の宅地開発が進み、釉薬にする材料の一部に、採れる場所がほとんどなくなってしまったものがあるそう。「現在は昔から使っているのと同じものが窯場の敷地内から採れるので、それを使うという感じですね。なまこ釉の白に使う籾殻灰(もみがらはい)は、親戚の農家からいただいています(久馬)」。
※江戸時代の名工・絵師で、野々村仁清のもとで陶技を学んだとされる。兄は琳派の旗手・尾形光琳。
-

針生家では成形のときに指を丸める。「一番安定する」という
-

4代・針生乾馬さん〈左〉。長男の久馬さん〈右上〉と次男の和馬さん〈右下〉
-

三浦乾也〈左写真中央〉に認められた初代〈同右〉が“乾馬”の陶号と『乾山秘書』(書き写し)を授かった。左は乾也の門人でロシア文学者の山口三平

ひとつの釉薬が満足いくまでに10年
柳宗悦も絶賛したというなまこ釉で知られる堤焼ですが、緑釉や他の釉薬もそれぞれに魅力があります。「60年以上前に日本民藝館のほうで堤の甕(かめ)を集めて常設してくれていることもあって、なまこ釉が堤焼の代名詞みたいになってますけど、なまこの甕を作っていたのは実は戦中ぐらいまでなんです。だからこそ私たちとしては、堤焼のそうした事実をなくさないよう、定期的に水甕を作って技術保存に努めています。緑のものが多く商品化されるようになったのは戦後になってからですね」と久馬さんは話します。
乾馬さんによると“辰砂(しんしゃ)”と呼ばれる独特な赤い色も、実は「もとは緑(の釉薬)」なのだそうで、「釉薬に銅が入っていると出てくる色」なのだといいます。「ひとつの釉薬が満足いくものになるまで、試行錯誤を繰り返して10年ぐらいかかるんですよ」と久馬さん。「なまこ釉、緑釉、灰釉、辰砂、鉄窯変、白窯変など、すべては父・乾馬や祖父、私の叔父、そして曾祖父、さらにその前の代と、ずっと前からの時代のなかで培われてきたものです」。
街の喧噪から離れた乾馬窯は、水鳥が訪れる沼や沢に隣接し、緑に囲まれた好環境にあります。「昭和39年からこの地でやっています。ここに移転してきたのは環境が良かったことはもちろんですが、台原の(粘土質の)地層がここまでつながっているとの地質学の先生のお話もあったんです。ここは自然が残っていて、なにより時間の流れがちょっと違いますね(久馬)」。「何にも代えがたくこの場所が好きです」と語るのは、次男の和馬さん。「周りがどんなに開発されても、ここはいつでもこの景色なんです。朝起きて目に入ってくる景色がずっと変わらないって、すごく幸せなことだと思います(和馬)」。
長い歴史のある堤焼ですが、伝統を受け継いでいくための取り組みとしては、「かたくなに教えてもらった昔のとおりにとやったのでは、たぶんだめですよね」と久馬さん。「いつの時代も守るところは守って、一方で少しずつ新しい要素を取り入れ、それが堤焼のスタンダードになってきた」といいます。
和馬さんは、「伝統工芸職人による“プロジェクト匠”というグループに参加して、展示会でいろんな新しい取組みを行っていますので、そこで反響の良かったものを定番にしていく、ということも出来る」と意欲的です。また、最近では器の基本的な扱い方がよく分からない人も多いそうで、和馬さんは「きちんと説明をして、長く愛用いただけるように、使ってくださる方々とのやりとりを大切にしていきたい」とも話します。
「土があって、形があって、釉薬があって、窯があって、使ってくださる方がいて、作る側の人がいて、総合して堤焼です」と語る久馬さん。「大きな物を作るだけでもだめですし、総合的にやっていかなければという思いがあるので、基本的な食器なども大事に作り続けていきたい。そうすれば少しずつでも前に進んでいけると思います」。「景気の良し悪しのせいだけにもしてられないし、地震なんて何十年に1回くらい来るのは仕方がないこと。そういう試練があったら乗り越えるしかないですよね」と潔い久馬さんをはじめ乾馬窯の皆さんは、常に未来を向いています。
-

焼くと赤茶色の部分が深い黒色に。釉薬にも地元の岩石などが使われている
-

現在は二人のお弟子さん(山口さん、高橋さん)が修業中
-

自然豊かな乾馬窯。冬にはすぐ近くの水辺に白鳥が飛来する
乾馬窯の個性が光る作品たち
-

乾馬さんの30年ほど前の作品。微妙な色味や独特の風合いは、登り窯ならではのもの。 窯変徳利花入れ
-

辰砂(赤)と白のコントラストに迫力を感じる4代・乾馬さんの作品。 辰砂窯変菓子鉢
-

明るく優しい色が目をひく久馬さんの作品。 緑釉抹茶碗〈左〉、藤彩釉薄器〈右〉
-

無駄のない形と爽やかな色合いが魅力の和馬さんの作品。 緑釉建水〈左〉、なまこ釉切立花入れ〈右〉