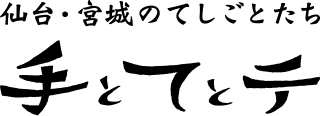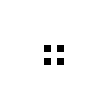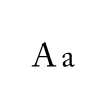久慈に生まれ、
久慈に寄り添う
久慈市は、リアス式海岸と
北上山地に囲まれた自然豊かな街です。
名物は、まめぶと琥珀。
NHK連続テレビ小説「あまちゃん」の
ロケ地にもなりました。
そんな街の山あい、
山里の林の中に小久慈焼の窯があります。
緑に囲まれた静かな工房で
ろくろを回す窯主、
下嶽智美さんにお話を伺いました。
原点は“日常使いの雑器”
小久慈焼の8代目、下嶽智美(しもだけさとみ)さんは幼いころから小久慈焼を見て育ちました。智美さんの父・毅(たけし)さんは、戦後途切れそうになってしまった小久慈焼の再興に奔走した人です。陶器ブームも手伝って小久慈焼は大いに盛り上がり、一時は30人以上の職人を雇うまでになりました。
「私が子どものころ、工房でたくさんの職人さんが作業していた様子はよく覚えていますね。陶芸も小久慈焼も嫌いだったわけではないのですが、当時はなぜか、跡を継ごうとは思いませんでした」。智美さんは久慈の高校を卒業後、仙台の大学に進学。インテリアデザインの会社に就職し、3年間勤務しました。実家に戻ったあとも、しばらくは陶器作りではなく、営業の仕事をしていたそうです。「東京の物産展に出店しても初めはなかなか売れませんでした。地方の小さな窯が東京で評価してもらうにはどうしたらいいか、と考えたのが器を作り始めたきっかけです。地方と東京では売れ筋が違うんだということに気が付くことができたんです」。
自分で器を作りたいと思うようになった智美さんは、昼間の仕事を終えたあと、ひとり工房で練習するようになりました。目指したのは小久慈焼きの原点です。「久慈は切り立った崖や深い山に囲まれた街です。今のように流通が発達していない時代から地元の人のために器を作り、使い勝手などの声を聞き、長い時間をかけて改良していったのが今の器の形につながっているのだと思っています。ハレとケで言えば、小久慈焼はケの器。あくまで日常の雑器であって、特別な日の器ではないんです。そういう原点を大切にした器を作ろうと思いました」。
<1>「気取らずに使える器がいいと思います」と話す下郷智美さん <2>今でも現役の登り窯 <3>先々代の熊谷龍太郎作の片口
現代の食卓にマッチする器を
現代の人々の生活にマッチする器を作るためにはどうしたらいいのか。智美さんが意識して取り組んだのはデザインのリニューアルです。「食卓の主役は料理。器はあくまでも料理を引き立てるための道具です。料理が洋なら、器も洋の方に寄って行くべきだと思うんですよね。私は、和と洋の隙間に入り込めるような器を作りたいと思っています。だって、今の食卓って、和と洋が一緒に並んでいるでしょ?ハンバーグとごはんとお味噌汁とか」。
そのために大事にしているのが、人の話を聞くこと。カフェやレストランとコラボしたり、若い人の意見を取り入れたりして、新しい形を模索しています。「器の形は昔から少しずつマイナーチェンジを繰り返してきました。私も昔からある形に、ちょっと手を加えているだけなんですよ。今人気のある皿も、これもベースは父の代からあった皿です。ふちの立ち上がりを少しシャープにしたり、角度を変えたり、少し手を加えるだけで洋食にも馴染むようになるんです」。
もうひとつ、大切にしているのが価格です。久慈の人たちが買える価格を守りたいと努力を重ねています。「スーパーの軒先で売っている一山いくら、みたいな陶器ほど安くするわけにはいきませんが、なるべく値段を上げないよう努力しています。すごく頑張らないと買えない陶器じゃ、普段使いはできないですから」。たくさん生産して値段を下げるため、型や電気ろくろも最低限使用しています。「仕上げや底の処理など、手をかけるところには手をかけて、任せられるところは任せる。そのバランスが大事だと考えています。手仕事のあたたかみまで失ったら、小久慈焼ではないですからね」。
<1>茶色が父・毅さんの大皿で、白色が智美さんの大皿。智美さんは縁の部分をアレンジした <2>弟子の中森吉隆さん <3>若い世代から支持を集める角皿は、レストランからの発注もある <4>おつまみや薬味を入れるのにちょうどいいサイズの角小皿
真っ白な粘土が小久慈焼の軸
人々の生活に合わせた柔軟な器づくりを心掛ける一方、智美さんがこれだけは変えてはいけないと考えていることもあります。粘土です。「小久慈焼の軸は粘土。この粘土を使っているから小久慈焼だと言っても過言ではないと思います」。
小久慈焼の粘土は久慈市の海岸沿いの地域、夏井町で採れるものを使用しています。「夏井町のあたりは、古い地層が隆起して地表近くに顔を出しているので、露天掘りでもいい粘土が採れます。粒子が細かいので、つるりとした感触に焼きあがるんです」。小久慈焼の粘土は鉄分か少なく、乳白色なのが特徴です。白の釉薬が素直に出るため、白い器もきれいに焼き上げることができます。
「粘土は月に400kgくらい使っています。粘土は掘ればなくなるものですが、小久慈焼の工房は少ないので、今のところ使うことができています。だからこそ、自分が守らないと、と思うんですよね。子や孫の代になっても、久慈の家には小久慈焼があるという環境を残したいな、と思っています」。
<1>掘ったままの状態の粘土。さらっとした触感 <2>灰釉に使う灰も、地元で作ったものを仕入れている <3>12月~3月は粘土が凍らないように電気毛布を掛けて保存するそう <4>市街地から少し離れた場所にある小久慈焼きの工房
引き立てる器、今むかし
-

7代・毅さん作の茶碗。リアス式海岸の風景をイメージした、でこぼこ模様が特徴。三陸のみやげ物として喜ばれた
-

昔からある中平碗の形を踏襲しながら、胴や高台をほんの少しシャープにして、洋食の食卓にも合うようにアレンジ
-

8代・智美さんの片口は、口が小さめですっきりした形。煮物を盛り付けたり、ドレッシングを入れたりするのにもぴったり
-

ストライプ調の櫛目がアクセントのフリーカップ。昔と変わらぬ釉薬を施しても、フォルムが違えば新鮮な印象に