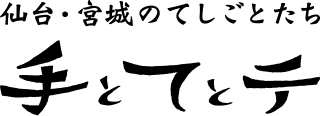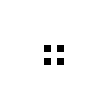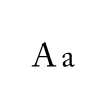地元の材料で、
そこに住む人々がつくる。
白石和紙を復興し、その伝統を守りつないだ遠藤忠雄さん。
その遺志を受け継ぎ、コウゾだけを使った手漉きの和紙がつくられています。
昭和初期、大量生産の洋紙におされて存亡の危機にあった白石和紙を救い、風土に根ざした手漉き紙の伝統を守りつづけた遠藤忠雄さん。優れた漉き手として白石和紙を有名にした忠雄さん亡き後も、妻・まし子さんが工房を引き継ぎ、ご家族や忠雄さんの技を受け継ぐ菊地さんらによって、手間ひまをかけ心を込めた和紙づくりが行われています。
昔から白石では、和紙の原料として地元産のカジノキ(コウゾの一種)を用いてきました。木肌に虎の模様のようなうぶ毛があることから“虎斑の楮(とらふのこうぞ)”とも呼ばれます。まし子さんによると、「繊維が細くて長く、やわらかい」のが特徴で、「伊達の分家の城下町・宇和島(愛媛県宇和島市)から伝わったとされている」のだそう。この良質な“虎斑の楮”と豊富なわき水があるからこそ、丈夫で美しい和紙がつくりつづけられてきました。「この地方で採れるもので、ここに住む人たちがつくる。和紙というのはまさに“地場産品”なんです(まし子)」。紙漉きには欠かせない、繊維の絡みを防ぐために入れるニレ(トロロアオイ/一般的にはネリとも呼ばれる)は、自家栽培のものが使われています。

白石和紙工房を切り盛りする遠藤まし子さんは、90歳とは思えないバイタリティーの持ち主。研究熱心だった忠雄さんのそばで様々なものを見聞きしてきたこともあり、知識や話題が豊富で訪れる者を飽きさせない
-


“虎斑の楮”(とらふのこうぞ)の太く立派な部分が原料として使われる
-


黄色い花をつける自家栽培のニレ〈左〉。ニレのヌメリが繊維の絡みを防ぎ紙をなめらかにする〈右〉
-


簀桁と呼ばれる道具を使って紙を漉く。菊地日出子さんは、この道30年以上のベテラン
-


“紙干し”の準備をする遠藤昭子さん。原料の下ごしらえは何十工程にもおよぶという
最も大切で難しいのは、
“ニレの肌かげん”。
東大寺・修二会の紙衣に用いられるなど、優れた品質で知られる白石和紙。
職人が微妙な手の感覚を頼りにこしらえた原料の溶液から、丁寧に漉き出されます。
優れた品質から、古くは太平洋戦争終結時の降伏文書に使われたほか、金刀比羅宮(香川県)の円山応挙障壁画の修復にも用いられた白石和紙。まし子さんは「用途によって、薄い・厚いを漉き分ける」と話します。もみほぐした和紙でつくる紙衣(かみこ)用には簀桁(すげた)を縦横に動かす“十文字漉き”、和紙でつくった糸で織る紙布(しふ)や書道用は、簀桁を縦方向だけに動かし漉き出すそうです。“十文字漉き”の強くふくよかな和紙は、長年にわたり東大寺(奈良県)の仏教儀礼・修二会(しゅにえ/通称“お水取り”)で修行僧の紙衣に用いられてきました。この紙に惚れ込んだファッションデザイナーの三宅一生さんが、白石和紙を使った「紙衣」(1982年)を発表したことでも知られています。
紙漉きで最も難しいのは、「ニレの混ぜ加減」と語るまし子さん。トロロアオイの根をつぶして出たヌメリを利用しますが、気温によって状態が変化しやすいそうです。「入梅の頃などはだめ、ニレの機嫌が悪いんです。濃度や状態を手で確かめるので、私たちは“ニレの肌かげん”といいますが、この調整が一番難しい。『1+1』のように単純にはいきません」。現在、“ニレの機嫌”をうかがえるのは、紙漉き担当の菊地さん唯一人。微妙な“肌かげん”を頼りに、伝統ある和紙が日々漉き出されています。
-


「特別にいただいた」という、東大寺・修二会で修行僧が着用した白石和紙製の紙衣
-


三宅一生さんがInternational Council 1985のために白石和紙でつくったヴェスト。羽織ると温かい
-


まし子さんが織った紙布織。紙布を織ることができる人は、現在はほとんどいないそう
-


忠雄さんの友人だった彫刻家・佐藤忠良さんによる刻書。白石和紙を好み“蔵王紙”と命名した日本画家・川合玉堂氏の書を見事に模刻している

ニレの働きによって、厚みを出すために重ねて乾かした和紙でも後からきれいに分けられる
※白石和紙工房は2015年3月をもって生産終了・廃業しました。現在、その技術や生産は市民グループ「蔵富人」に継承されています。