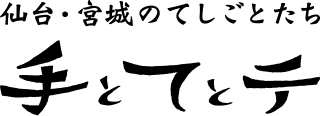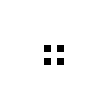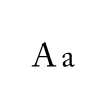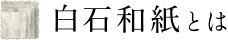白石和紙とは
地元産の楮から手しごとで生み出される
強くてふくよかな伝統ある手漉き和紙
紙をつくる技術は、仏教の伝来とともに中国から朝鮮半島を経て日本に伝わったとされている。その後、日本気候風土に育まれながら独自の発展をとげ、“流し漉き”による強くて美しい和紙が生み出された。平安時代に東北一帯(陸奥国)でつくられた和紙は京都にも運ばれ、ふくよかで格調高い“みちのく紙”として紫式部や清少納言も愛用したという。
その“みちのく紙”の流れをくむ白石和紙は、伊達藩主とその家臣で白石城主の片倉家による奨励・保護のもとで発達。片倉領内の農民たちの農閑期の内職として、地元で採れる良質の楮(こうぞ)を用いた紙が漉かれ、地域を代表する名産品となっていった。もみ込んで柔らかな布のようにした和紙を着物などに仕立てた紙衣(かみこ)や、和紙を細く裂いてつくった糸で織る紙布織(しふおり)も産してその上質さで知られたが、明治以降に工場生産の洋紙が広く出回ると和紙づくりは衰退を余儀なくされた。
一時はほとんど廃れてしまった白石和紙だったが、昭和初期に、代々続く紙漉き農家の8代目・遠藤忠雄が、地元産の楮を原料とする伝統的な手漉きの和紙づくりを再興。手間ひまをかけた古来の製法で、心をこめて漉き出された白石和紙は後に再び全国的な注目を集め、重要文化財修復用紙や奈良・東大寺“お水取り”(修二会)の紙衣としても利用されるようになった。遠藤は、片倉信光(片倉家15代)らと郷土の伝統文化の調査・研究を行う“奥州白石郷土工芸研究所”を結成。そのメンバーだった佐藤忠太郎が中心となり、昭和23年頃、こんにゃく粉を溶いた糊を塗って強化した和紙に型板で模様をつける“拓本染め”が生み出され、紙衣の素地である紙子(かみこ)も復活した。
現在も、遠藤の妻まし子が白石和紙工房で手漉き和紙づくりの伝統を守り、2軒の紙子工房が拓本染めの技を受け継いでいる。郷土を愛した人々が懸命につないだ白石和紙の灯火が、消えることなく続いていくことを地域の誰もが願い、見守りつづけている。
白石和紙工房
- 住所:
- 宮城県白石市鷹巣東3-1-6
- 電話:
- 0224-26-3333
※白石和紙工房は2015年3月をもって生産終了・廃業しました。
現在、その技術や生産は市民グループ「蔵富人」に継承されています。