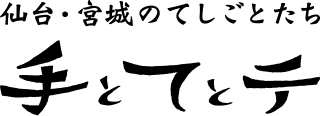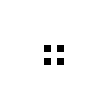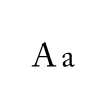昔は宮城県内の一家に
一棹はあったといっても
過言ではない仙台箪笥。
丈夫で美しい箪笥は母から子へと
代々受け継がれていました。
そんな素晴らしい仙台箪笥を愛し、
守るために邁進する2人の職人のお話。
感動、憧れから志した
木工への道
木の性質をじっくりと見極め、箪笥のベースとなる木地を仕上げていくのが指物師の仕事。杉林に囲まれた工房『木香舎(もっこうしゃ)』の増野繁治さんは仙台箪笥の受注はもちろん、その指物技法をいかし、天然木を使うことにこだわった注文家具を製作・販売しています。最近では2012年に保存復原が完成した、国の重要文化財である「東京駅丸の内駅舎」の3階ドーム部分の窓やドア等も手がけました。そんな増野さんが木工の世界に飛び込んだのは小学生の時に東京で行われた正倉院展を見たことがきっかけだったそう。「奈良時代、天平文化を代表する、当時の天皇が使っていた調度品の数々にびっくりしました。1300年以上も前からこんな素晴らしいものがあったのかと。その中でも、長い時を経ても輝きを放っていたのは木工品でした。金銀財宝、宝石よりも、木工っていうのはすごいなとその時思いました」。
増野さんが幼いころを過ごした東京・蒲田の土地柄にもルーツが。「職人さんがいっぱいいて、映画館があった。そこで色んな外国映画を見ました。映画の中には必ずといって良いほど椅子やテーブルが出てくるんだよね。そこで役者がカッコ良くウイスキーを飲んでたりする。そういうのを見ていいなぁって思いましたね。当時、普通の家庭にあった家具といえばちゃぶ台くらいでしたから。家具を注文する、使うっていうことは本当に素晴らしいこと。映画を見て、世界の俳優が使う家具を作りたいと思いました」。
郷土の誇りと
自慢の仙台箪笥
木工、家具の世界に憧れた増野さんが初めて仙台箪笥に出会ったのは昭和45年頃のこと。「当時、平均月給が7万円くらいの時代。日本橋三越で、年収200万円に満たない人がほとんどの時代に、初めて目にした仙台箪笥は一棹が250万円くらいしたんです。その当時の日本はどんどん景気がよくなり、所得倍増計画などといわれていて、年収も増えつつある時代だけれど、250万円という価格はやはり高額。どうしてそんなに高いんだろう?と驚いたんだけど、細部まで見るとそれもうなずける素晴らしいものでした」。
仙台箪笥の魅力に惹きつけられた増野さんは高校を卒業後、東京を離れ仙台で仙台箪笥の職人に師事。家具職人としての第一歩を踏み出しました。当時、仙台箪笥はほとんどが受注生産。嫁入り道具として求める人が多かったそう。「デパートの催事で婚礼箪笥フェアのような企画が行われて、そこにお嫁に行く人が家族と一緒にやってきて、箪笥を注文していくという形が多かったです。結婚する子のために家族が思い託して箪笥を求めるという、すごく楽しい、いい時代でした。家具はその人と一緒に物語を綴っていってくれるものですからね」。
いい材を使い、材を知ったるの職人が手がける仙台箪笥は、数代にわたって使い続けることができるといいます。それ故に、箪笥一棹の価格は決して安いとはいえません。「もちろん、誰もが買い求められるものではないですよね。だからといって価格を下げるために工場で生産された合板を使ってしまったら、巷で売られている工業製品と同じになってしまうと私は思っています。そこに伝統はないですから。海外にも通用する素晴らしいものが仙台にあるんだという事実、歴史を知っていてもらうだけでも素晴らしいこと。仙台箪笥を買い求めた人がいたら、『あの工芸買えたんだ!すごい』って思ってもらえるようになったら素敵でしょ。私は文化ってそういうことだと思っています」。木工の道を歩むきっかけとなった仙台箪笥への思いを胸に大切に抱きながら、買い求めた人と一緒に人生を歩んでいく家具の製作に取り組んでいます。

木材は自らの目で選んで宮城県の森林組合等で入札し、仕入れている。じっくり乾燥させるので、製品で使うためには数年かかる
〈1〉美しい木目の無垢材だけで製作する家具は長い年月使い続けることができるという 〈2〉木のクセを見ながら、木取りから組み立てまで細やかな技で箪笥を仕上げていく 〈3〉使う人がどういう家具を求めているのかカウンセリングしながら、その人の考え方や生き方に寄り添う家具作りを信条に掲げて仕事をする増野さん

増野繁治さん
昭和33(1958)年、熊本県天草生まれ。千代鶴延国のもとで鉋鍛冶を学び、高校卒業後、仙台箪笥職人・渡辺俊夫に師事。宮城県デザインコンクールほか数々の受賞歴を誇り、平成14(2002)年には林野庁の「森の名手・名人100人」に選定された。
工房 木香舎
宮城県黒川郡富谷町穀田字瀬ノ木113
TEL 022-358-1141
http://www.mokkousya.com/
伝統を伝えていくということ
仙台箪笥の伝統的な塗り方である木地呂(きじろ)塗は時の流れとともに漆の透明度と赤みが次第に増していき、より味わい深いものになっていくのが特徴。生地の美しい木目が活きてくるこの塗をしっかりと仕上げられる職人も数少なくなってきました。代々続く漆工の家庭に生まれた長谷部さんはそんな数少ない職人の一人。若い頃から父に師事し、仙台箪笥の塗師としての技術を研鑽してきました。現在は長谷部さん自身が若い従業員を雇用し、技術の継承に努めています。「昔は一般的に弟子入りしてから一人前に仕事が任されるようになるまでは最低でも5、6年かかったといわれています。徒弟制度といって、親方のもとで住み込みで修行して、休みもろくになく、朝から夜中まで仕事するのが当たり前でした。今はそういう時代ではないですけどね(笑)。伝統工芸といっても、技術をより良い形で生かして、今の生活様式に合ったものづくりをしていくということが大切。若い人たちが持っている感覚、新しいものとの融合ということが自分にも必要なんじゃないかと思っています」。
指物師、彫金師、塗師、三者の技術の結晶ともいえるのが仙台箪笥。身近な生活財として愛用されていましたが、生活環境の変化等に伴ってその数は減少し、若い世代の認知度も低いのが実情と長谷部さんは語ります。「ほんとうに箪笥が売れなくなって、『そういった箪笥あったよね』と、過去形になってしまったのでは次の時代に伝わらないですし、一度途絶えたものを復活させるのは難しいと思うのです。だから今の技術が残っているうちに、いろいろな仕掛けをしながら仙台箪笥を次の世代に伝えていきたいと思います」。
職人同志の柔軟な
発想のものづくり
長谷部さんの工房の敷地には修理を待つ古い仙台箪笥が所狭しと並んでいます。それらは2011年に起きた東日本大震災以降に運び込まれたもの。「今は修理の依頼がほとんどで、その大半が震災の影響で壊れた箪笥です。海水に浸かってしまったり、揺れでゆがんでしまったり。その中にはかなり古いものも含まれていました。改めて、仙台箪笥というものは世代を超えて大切に受け継がれているものなんだなと実感しましたね」。箪笥は一度、解体されて組み直し、金具も可能な限り再利用。そして味わい深く美しい塗りが施されて持ち主のもとへ帰ります。
長谷部さんは現在、若手の木工職人、家具デザイナーと一緒に、「DACCIA(ダッチア)」というものづくりユニットで活動しています。そこに内包される形で進行する「DATI(ダティ)」は古い仙台箪笥をリデザインするという再生プロジェクトで、この取り組みは2013年のグッドデザイン賞を受賞しました。「仙台箪笥はもともと刀や裃(かみしも)、着物を収められるよう作られていたのでとても大きいものです。マンション暮らしでコンパクトな住まいの家庭には不向き。そこで箪笥を半分のサイズにしてローチェストなどに仕上げ、現代の暮らしにも合うように再生しています。こういった取り組みをすることで、仙台箪笥の魅力をより多くの人に知ってもらえればいいなと思います」。ライフスタイルの変化に伴う需要の低迷、後継者不足など、仙台箪笥を取り巻く環境は厳しい中、柔軟な頭で仙台箪笥の未来を前向きに、まっすぐ捉えていました。

仙台箪笥の木地呂塗で使う生漆。国産の漆が採れなくなってきているので、今は国内に出回る8割が中国産になっているという
〈1〉塗っては磨き、磨いては塗るのを繰り返し、漆を重ねていく根気のいる作業 〈2〉修理では古い箪笥から外した金具のサビを落とし、漆を塗って焼付け、美しく再生させる。金具も極力昔のまま再生させるという 〈3〉修理を待つ古い仙台箪笥。金具などもすべて取り外し、仕上げるまでは半年ほどかかる

長谷部嘉勝さん
昭和27(1952)年、宮城県仙台市生まれ。創業万延元年(1860年)の長谷部漆工の十二代目として仙台箪笥の塗りに携わる。鎌倉彫教授会認定の鎌倉彫皆伝教授を取得後、宮城県芸術家協会で宮城県知事賞をはじめ受賞歴多数。
(有)長谷部漆工
宮城県仙台市青葉区郷六字葛岡下10-4
TEL022-302-1505